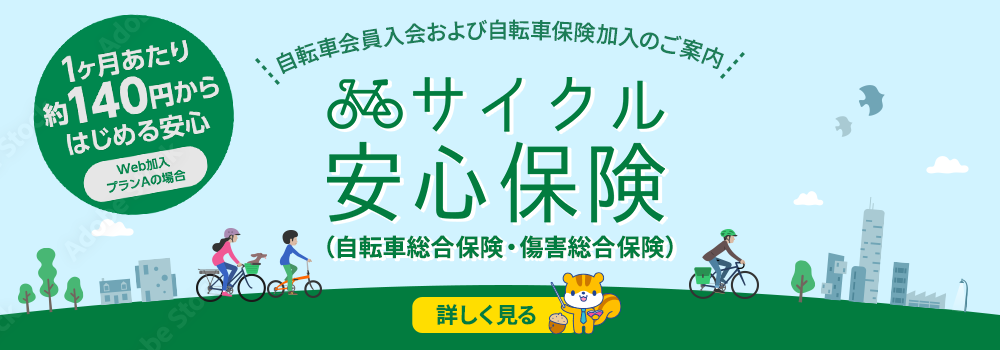もうすぐ梅雨の季節。雨が続く梅雨の季節、自転車通学や通勤をしている方にとっては悩ましい時期ですよね。滑りやすい道路、濡れたブレーキ、見えにくい視界——実は、梅雨は一年の中でも自転車事故が急増するシーズンなんです。
特に子どもが自転車を利用する家庭では、「転倒してケガをした」「他の人にぶつかってしまった」など、雨がきっかけの事故が思わぬ大事につながることも。
今回は、梅雨時の自転車に潜むリスクとその対策を、家庭でできる安全行動とから保護者として備えておきたい事まで幅広く解説します。
- 雨の日の自転車通学などで気をつけるポイントは?
- 子どもにどんなルールを教えるべき?
- 自転車保険は必要?
そんな疑問にもわかりやすくお答えしていきます。「事故を防ぐ行動」と「万が一に備える仕組み」——その両方を整えて、梅雨を安心して乗り切りましょう。
1.雨の日の自転車は危険が倍増!5つの主なリスクとその背景
梅雨の時期、自転車に乗るだけで「いつも通り」が「一気に危険な状況」に変わります。雨がもたらす5つのリスクは、特に小中学生の通学時にこそ注意が必要です。
ここでは、雨天時に気をつけたい代表的なリスクと、その背景についてご紹介します。
1-1. ブレーキ性能の低下と制動距離の増加
雨で濡れたブレーキは、乾いた状態に比べて効きが明らかに悪くなります。制動距離(止まるまでの距離)が1.5倍〜2倍ほど伸びることもあり、「いつもの感覚で止まろうとしても間に合わない」ことが起きやすくなります。
特に下り坂では、スピード+水による摩擦の減少により、止まらない・転倒するリスクが急上昇。小学生などは握力が弱いため、ブレーキをしっかりかけられず、そのまま進んでしまうケースもあります。
1-2. 視界不良による反応の遅れ
レインコートのフードやフロントの透明部分に水滴がつくと、前方の視界が曇ります。さらに、眼鏡をかけている子は、二重に曇りや水滴の影響を受けるため、危険の発見が遅れてしまいがちです。
特に朝夕の薄暗い時間帯では、歩行者や他の自転車との接触リスクが高まります。「見えていなかった」「遅れて気づいた」というわずかな遅れが、事故の原因になるのです。
1-3. 路面の滑りやすさ
濡れた道路は、乾いた路面よりもタイヤが滑りやすくなります。特に滑りやすいのが以下の場所です。
- 横断歩道の白線部分
- マンホールや金属グレーチング(側溝のフタ)
- タイル・石材の歩道(駅前や商業エリアに多い)
見た目ではわからなくても、こうした素材は水を含むと極端にグリップ力が下がるため、スリップ事故が発生しやすくなります。
タイヤの空気圧が低かったり、ブレーキの調整が甘い自転車では、さらにリスクが増します。
1-4. 視認性の低下
自転車に乗る側が見えづらくなるのと同時に、自転車に乗っている人自身が他者からも見えにくくなるという問題もあります。
特に暗めのレインコートや制服を着ていると、車やバイクのドライバーからの視認性が大きく下がります。結果として、「そこに人がいる」と気づいてもらえず、接触事故につながるケースも。
雨の日は、車のワイパーや窓の曇り、暗さ、反射の多さなど、周囲の認識力も低下しているのが現実です。
1-5. 雨音や風による「聴覚情報の欠損」
もうひとつ見落とされがちなリスクが、「音が聞こえにくくなること」です。
レインコートのバサバサ音、フードで覆われた耳、そして雨や風の騒音、こうした要因が重なり、後ろから来る自転車や車に気づきにくくなる状況が生まれます。
雨の日に多い「気づいたら真横に自転車が来ていた」「後ろからクラクションが聞こえなかった」といった声の背景には、この“聴覚の遮断”があります。
2.実際に起きた「雨の日の自転車事故」実例
雨の日の自転車通学は、通常よりも多くの危険が潜んでいます。ここでは、実際に発生した事故の事例を通じて、どのような状況で事故が起こり得るのかを見ていきましょう。
【事例1】小学生が通学中に転倒し、鼻骨を骨折
小学生男子が登校中にハンドルにぶら下げていた雨がっぱを入れた袋が前輪に絡まり転倒。
その際、頭部からコンクリートの地面にたたきつけられ、鼻骨を骨折する中等症のけがを負いました。
この事故は、雨天時における自転車・雨具の取り扱いの危険性を示しています。
出典:国民生活センター「自転車用レインウェアの運転への影響と安全性について
【事例2】中学生が下り坂でブレーキが効かず転倒し、負傷
通学中の中学生が、雨でぬれた坂道を自転車で下っている際、ブレーキが効かずに転倒し、負傷しました。
事故後、自転車のブレーキワイヤーの張りを調整すると正常に機能したことから、ブレーキの調整が不十分な状態で走行していたことが原因と考えられています。
出典:製品評価技術基盤機構(NITE)「Vol.378 自転車の事故」
【事例3】高校生が傘差し運転で歩行者に衝突し、重度の後遺障害を負わせる
男子高校生が部活動を終えた午後7時、急に降り出した雨の中を自転車の傘差し運転で帰宅中、前方の確認をせずに運転していたところ、前を歩いていた83歳の女性に背後から衝突。
女性は転倒して頭を強打し、重度の後遺障害が残りました。
この事故は、傘差し運転の危険性と、歩行者への配慮の重要性を示しています。
出典:高知県「交通事故の事例−10.自転車が加害者となった事故」
これらの事例から、雨の日の自転車通学には通常以上の注意が必要であることがわかります。次は、雨天時における自転車の安全運転のポイントについて詳しく解説していきます。
3.雨の日の自転車安全運転10のチェックリスト
「いつもの道」でも、雨が降るだけで危険度は一変します。特に通学時は、急いでいたり、慣れた道だからこそ油断が生まれがちです。
雨の日の事故を未然に防ぐために実践したい10のポイントを見て行きましょう。
- ブレーキは「早めに・段階的に」かける
- スピードはいつもの「半分」を目安に
- 滑りやすい場所を把握して避ける
- 視認性の高いレインウェアを選ぶ
- 傘さし運転・スマホ操作は絶対NG
- ヘルメット+レインカバーで頭部もガード
- 雨の日ルートを事前に確認しておく
- 自転車の整備は“雨の前”にしておく
- いつもより「5~10分」早く出る習慣を
- 「今日は乗らない」という選択肢も持つ
3-1. ブレーキは「早めに・段階的に」かける
雨の日は、ブレーキパッドが濡れることで摩擦力が低下し、止まりたい場所でピタッと止まれないケースが非常に多くなります。
特に通学中の道は慣れていて油断しがち。いつもの距離感でブレーキをかけると、「あれ?止まらない!」という状態になり、慌てて転倒する事故につながりやすいのです。
そのため、ブレーキは止まりたい場所の2~3メートル手前から、徐々に力をかけて段階的にかけるのが鉄則です。急にギュッとブレーキをかけると、タイヤがロックしてスリップしたり、前輪だけかけて転倒する可能性もあるので要注意。
特に子どもは、まだブレーキの使い方が未熟で、焦ると前輪ブレーキを強くかけてしまう傾向があります。日頃から、「ブレーキは後輪を先に、前輪は軽く添える程度」といった使い方も教えておくと効果的です。
3-2. スピードはいつもの「半分」を目安に
通学中の子どもたちは、「遅刻しそう」「友達に追いつきたい」などの理由で、ついスピードを出してしまいがちです。
しかし、雨の日にそのままの速度で走行すると、路面状況に気づいたときにはもう止まれないというケースが起きやすくなります。
ブレーキが効きにくくなるのに加え、マンホールや白線で滑るリスクも増えるため、スピードを通常の半分に抑える意識がとても重要です。
「早めに家を出る習慣」も、このリスクを減らすための有効な対策です。家族で、「雨の日は5~10分早く出発する」をルールにすれば、スピードを出さなくても安心して通学できます。
また、「急がないための服装」も大切。防水機能の高いレインコートやカバーカゴを使えば、荷物が濡れる不安が減り、落ち着いて運転できる環境を整えられます。
3-3. 滑りやすい場所を把握して避ける
雨の日に事故が起きやすいのは、ただ濡れているからではありません。濡れた特定の素材が“極端に滑りやすくなる”ことが原因である場合が多いのです。
たとえば以下のような場所は、雨天時の滑りやすさが段違いです。
- 横断歩道の白線:塗装された部分は濡れるとツルツルに
- マンホールの蓋:金属はグリップ力ゼロ
- 側溝のグレーチング:細かいスリットでバランスを崩しやすい
- 駅前のタイル:ツルっとした石材が使われているケースも
こうした場所でブレーキをかけたり、カーブを曲がると、滑って転倒するリスクが非常に高くなります。
実際に事故が起きた例として、小学生が白線の上でスリップし手首を骨折した事例もあります(第2章参照)。このような事例をもとに、親子で通学ルートを一緒に歩き、「雨の日に危ない場所」をマップ化しておくことも安全対策として非常に有効です。
3-4. 視認性の高いレインウェアを選ぶ
雨の日は周囲の視界が悪くなるうえ、車のドライバーの注意も散漫になりがちです。そんな中で黒や紺などの暗い色のレインコートを着ていると、子どもの存在が他人から見えづらくなってしまうという大きなリスクがあります。
自転車に乗っている自分が見えていないだけでなく、車や歩行者から「見落とされる」という二重の危険があるのです。
そのため、レインウェアは「濡れない」だけでなく、「目立つこと」も重要な基準になります。おすすめは、黄色・水色・オレンジなどの明るい色で、反射材(リフレクター)付きのもの。特に小中学生の通学用には、背中・袖・足元などに反射テープがついているタイプがベストです。
また、フード部分には視界確保用の透明窓があるものを選ぶと、左右や下方向の視野も広がり、飛び出しや巻き込み事故を防ぎやすくなります。
価格帯はさまざまですが、1,000〜3,000円台でも機能的なものが多く、「視認性は命を守る投資」として考えておきたいポイントです。
3-5. 傘さし運転・スマホ操作は絶対NG
雨の日の自転車事故で非常に多いのが、「片手運転」による事故です。傘を差した状態では、視界が狭くなるうえに両手でハンドルを持てず、バランスも大幅に低下します。
また、風で傘があおられると一気に操作不能になり、急に転倒したり歩行者にぶつかったりする危険もあります。
これらの行為は道路交通法で明確に禁止されており、警察に見つかると交通違反として指導や罰則の対象になる可能性もあります。
同様に、スマートフォンの操作やイヤホンの使用も極めて危険です。雨音の中ではそもそも周囲の音が聞こえにくくなるため、さらに注意力を削ぐ行動は命に関わります。
「ちょっとくらいなら大丈夫」は、雨の日の自転車では通用しません。家庭でも、「雨の日は絶対に両手で運転・スマホ禁止」をルールとして明確に伝えておくことが大切です。
3-6. ヘルメット+レインカバーで頭部もガード
雨の日の転倒は、晴天時よりも頭を強く打つ事故の割合が高いとされています。ぬれた路面での転倒はコントロールを失いやすく、勢いそのままに頭部から地面に打ちつけてしまうことがあるためです。
自転車に乗る子どもにはヘルメット着用が義務化されつつありますが、雨の日にはそこに防水用のヘルメットカバーを併用することがおすすめです。
ヘルメットカバーは100円ショップなどでも購入でき、取り外しも簡単。雨を弾くだけでなく、視認性の高い色や反射プリントがついているものもあり、安全性と快適性を同時に高めるアイテムです。
また、濡れた状態のヘルメットを放置してしまうとカビや劣化の原因にもなるため、使ったあとはしっかり乾かし、定期的に状態をチェックする習慣も家庭で共有しておくとよいでしょう。
3-7. 「雨の日ルート」を事前に確認しておく
晴れているときは気にならない道も、雨が降ると急に危険な通学路に変わることがあります。たとえば、水たまりができやすい道路、道路脇がぬかるみになる道、路面にヒビがある坂道などは、雨の日に特に注意が必要です。
親子であらかじめ「雨の日に滑りやすい場所」や「見通しの悪い交差点」などを一緒に歩いて確認しておきましょう。
できれば、晴れの日と雨の日の両方でルート確認をしておくのが理想です。
「ここはいつもよりゆっくり進もうね」「この道は雨の日だけ避けよう」など、家庭内で共有する“安全ルール”を持つことが事故防止に直結します。
3-8. 自転車の整備は“雨の前”にしておく
梅雨の時期に入る前に、自転車の整備はしっかり済ませておきましょう。
特に注意したいのは以下のポイントです。
- ブレーキの利き具合(前後とも均等に効くか)
- タイヤの溝・空気圧(すり減っていたら滑りやすくなります)
- ライトや反射板の点灯確認(見られる・見える両面が大事)
雨の日は、普段よりブレーキやタイヤに負荷がかかるため、ちょっとした整備不良が重大事故につながるリスクが高まります。
また、チェーンのサビやブレーキワイヤーの伸びなどは自分では判断しにくいので、年に1〜2回は自転車店でプロに見てもらうのが安心です。
お子さんが通学で使っている自転車ほど、「壊れてから直す」ではなく、「壊れる前にチェック」が鉄則です。
3-9. いつもより「5~10分」早く出る習慣を
雨の日は、思っている以上に移動時間がかかるものです。靴が濡れたり、傘の開閉があったり、自転車に乗る前後もバタつきます。
そのため、雨の日は「急ぐ」前提ではなく、“早く出る”前提で準備することが安全への第一歩。特に通学時は「遅刻しそうだからスピードを上げて走る」という状況をつくらないことがとても大切です。
家庭で「雨の日は○分早く出る」をルール化し、アラーム設定や出発の声かけも活用してあげましょう。「急がない環境」をつくることで、事故のリスクをぐっと下げることができます。
また、余裕を持って出発することで、落ち着いた運転・判断力の余白も生まれます。
3-10. 「今日は乗らない」という選択肢も持つ
雨の強さや風の状況、視界の悪さによっては、そもそも自転車に乗るべきでない日もあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 台風の接近で突風が吹いている
- 横殴りの雨で視界がほとんどない
- 路面に川のような水が流れている
そんな日は、「無理してでも自転車で行かないと…」ではなく、「今日はやめよう」という判断が、家族を守る選択になります。
通学であれば、保護者が途中まで送っていく、公共交通機関に切り替える、徒歩に変更するといった柔軟な対応を検討しましょう。「雨でも自転車」が当たり前になってしまうと、子どもは「危ないからやめよう」という判断を持ちにくくなります。
家庭であらかじめ、「この天気なら乗らない」という基準を決めておくことも、事故防止に非常に有効です。
4.親としてできる事故予防と心の準備
梅雨時期の自転車通学は、たとえ毎日の慣れた道であっても、思いがけない危険が潜んでいます。
その危険を回避するには、「自分で考えて行動できる子」に育てると同時に、家庭内での明確なルールを決めておくことが大切です。
4-1. 子ども任せにしない「家庭でのルールづくり」が事故を防ぐ
たとえば、「雨の日はこのルートを通る」「滑りやすい道は遠回りしてでも避ける」「視認性の高いレインウェアを着る」といった具体的な決め事があると、子ども自身も迷わず行動できます。ルールは親子で一緒に話し合って決めることで、「守らされている」ではなく「自分ごと」として理解しやすくなります。
また、学年が上がって自立してきたタイミングほど、もう一度一緒に「雨の日の行動計画」を見直すことも有効です。
4-2. 「出発前の一言」が子どもの意識を変える
どんなに前日までに準備していても、朝のバタバタで忘れてしまうのが子ども。だからこそ、親からの一言の声かけが効果的です。
「今日は濡れてるからブレーキ早めにかけてね」
「マンホールの上は滑るから、避けるんだよ」
「反射テープ、ちゃんと見えてるね」
ほんの数秒の声かけでも、子どもの意識をぐっと引き締めることができます。これはしつけというより、習慣づくりの一環として日常に組み込むのが理想です。
特に雨の日は、朝から気分が沈みがち。親の「気をつけてね」の一言が、安心材料になり、注意力を上げるきっかけになります。
4-3. 「加害者になるかもしれない」リスクも家庭で共有を
雨の日の事故は、自分がケガをするだけではなく、他人をケガさせてしまうリスクもあります。特に通学中、歩行者にぶつかったり、友達同士で接触してしまったりするケースは少なくありません。
その結果、損害賠償責任を負ったり、相手の家族とのトラブルに発展したりといった事例も実際に発生しています。子ども自身にそのリスクを重く感じさせる必要はありませんが、「万が一、相手にけがをさせてしまったらどうする?」と一緒に考える時間を持つことはとても大切です。
こうした話し合いを通じて、子どもは“自分の運転に責任がある”という感覚を少しずつ身につけていきます。
4-4. もしもの備えを「事前に」しておくことが親の責任
どんなに注意していても、事故は起こる時には起こります。それが自分の不注意でなくても、責任が問われることは少なくありません。
だからこそ、事故が起きたときの対応を家庭で共有しておくことが、親としての大切な準備になります。
- ケガをさせた・した場合、まず誰に連絡するか
- 通学中の事故なら学校と連携する流れは?
- 保険には加入しているか、補償の範囲は十分か?
これらの情報を親が把握し、必要であれば子どもにも簡単に伝えておくことで、万が一の際にも落ち着いて行動できます。
次は、こうした「万が一の事故」に備える方法として注目されている、自転車保険の役割と価値について詳しくご紹介します。家庭の経済的・心理的な負担を軽減するための備えとして、とても大切なポイントです。
5.“もしも”に備えるのが親の責任——自転車保険という選択
雨の日の事故は「自分が悪くなくても」責任が生じることがあります。自転車事故は、たとえ本人が細心の注意を払っていても、避けられないケースも。
例えば、自分が滑って転倒し、その拍子に隣を歩いていた人にぶつかってしまった。あるいは、突然目の前に飛び出してきた歩行者と衝突してしまった。こうしたケースでも、自転車側が「加害者」として扱われることが多く、責任を問われる可能性は高いのです。
特に雨の日は、路面状況や視界の悪さから事故の責任が一方的にこちらにかかってくることもあり得ます。つまり、「気をつけていても責任を負う立場になる」ことが、雨の日の大きなリスクなのです。
5-1. 子どもが加害者になった場合、保護者が賠償責任を負う
未成年の子どもが事故を起こした場合、法律上は保護者が監督責任を問われることになります。これは「監督義務者責任」と呼ばれ、仮に加害者が小学生でも、賠償金の請求は親に対して行われます。
実際、過去には中学生が歩行者と衝突し、約9,500万円の損害賠償を命じられた判例もあります。(神戸地裁 2013年7月4日判決:11歳男児による自転車事故)
このような高額な請求は決して珍しいことではなく、事故の内容によっては数十万〜数千万円規模の賠償が必要になることもあります。つまり、「まさかうちの子が」と思っても、ひとたび事故が起これば、家庭の経済に深刻な影響を与える可能性があるのです。
5-2. 自転車保険なら、費用も交渉もプロが対応してくれる
こうした「万が一」の事態に備えるために、注目されているのが自転車保険です。自転車保険に加入しておくと、以下のような補償が受けられます。
- 他人にけがをさせた場合の損害賠償費用(1億円以上まで補償されることも)
- 自分や子どもがけがをした場合の入通院費用・入院一時金
- 示談交渉や被害者対応を保険会社が代行
- 通学で義務化されている学校への保険証明書の提出にも対応可能
保護者が一から対応しなければいけない状況とは違い、専門の担当者が間に入って対応してくれることで、精神的負担も大きく軽減されます。事故後に「どうすればいいかわからない」という混乱を回避する意味でも、保険のサポート体制は非常に心強いものです。
5-3. 月数百円で家庭を守れる“コスパ最強の備え”
自転車保険の保険料は、意外にも月額200円〜500円前後と、非常に手頃です。それでいて、加害者になった場合の1億円規模の賠償や、被害者になった場合の医療費、入通院の補償までもが含まれているプランが多く、「保険料の何百倍もの安心」を得られるコストパフォーマンスがあります。
家族で加入できる“家族型”のプランを選べば、親子全員が1契約でカバーできるので、複数人分を別々に契約するよりもずっと割安です。
万が一に備えることはもちろん、今後自治体や学校での加入義務化が広がることも考えると、早めの加入が安心にもつながります。
6.自転車保険の費用感と内容例
自転車保険に対して「お金がかかりそう…」という印象を持つ方は少なくありません。ですが実際には、月額300円〜500円程度で加入できるものがほとんどで、保険としては非常に手頃な価格帯です。
今回は、当社がおすすめしている損保ジャパンのサイクル安心保険を例に説明して参ります。
6-1. 月額わずか140円~!家計にやさしい自転車保険
JTSA自転車保険(サイクル安心保険)は、年間1,670円~(月あたり約140円)から加入可能。
「事故のときだけ使う高額な保険」と思われがちな自転車保険ですが、この保険なら手頃な価格でしっかり備えられるのが特長です。
プランは3種類あり、家族の構成や補償内容に合わせて選べます。
- プランA:最もシンプルな基本補償
- プランB:個人向けにケガの補償も追加
- プランC:家族全員が補償対象になる、安心の家族型
6-2. 賠償責任は最大1億円、しかも示談交渉つき
全プラン共通で、国内での賠償責任1億円+示談交渉サービス付き。
万が一、通行人にケガをさせてしまった、他人の塀を壊してしまったといった場合も、保険会社が交渉を引き受けてくれるので、精神的な負担を大きく減らせます。
これは子どもが事故を起こした場合でも同様で、保護者が前面に立って被害者対応をしなければならない負担を軽減してくれます。
6-3. ケガの補償はプランB・Cで対応
- プランA:賠償責任のみ(ケガの補償なし)
- プランB(個人型):死亡・後遺障害1,000万円/入院日額3,000円(本人のみ)
- プランC(家族型):本人:死亡・後遺障害1,000万円/入院日額6,000円
家族:死亡・後遺障害850万円/入院日額6,000円
プランCでは、配偶者や子どもも含めて同じ内容の補償が適用されるため、通学・通塾をするお子さんがいる家庭には特におすすめです。
- お子さんが自転車通学・塾通いをしている
- 万が一の事故に備えて、家庭全体を守りたい
- 加害者になってしまった時の費用や交渉が不安
- すぐに保険証明書を提出する必要がある
このような方には、手続きの簡単さと補償の手厚さを両立したサイクル安心保険がぴったりです。
7.ネットで簡単!申し込み手順とおすすめ保険
「保険って面倒くさいんじゃないの?」
そんなイメージを持っている方も多いかもしれませんが、JTSA自転車保険はスマホやPCから誰でも簡単に加入可能です。
書類の記入や郵送の手間は一切なし。手続きにかかる時間はわずか3分程度で完了します。
申し込み完了後には、その場ですぐに加入証明書をダウンロードできるため、学校への提出もその日中に対応可能です。
7-1. 【スマホで簡単!】実際の申し込み3ステップ
JTSA自転車保険の申し込みは、以下のステップで完了します。
- 専用ページにアクセスする
⇒ JTSA自転車保険の申込みページはこちら - メールアドレスを入力し、届いた案内に沿って必要情報を記入
⇒ 契約者の氏名・住所・生年月日などを入力します
⇒ 希望プラン(A/B/C)を選択、クレジットカード情報を入力 - 決済が完了すると、加入証明書をPDFでその場で取得可能
⇒ ダウンロード or メール送信に対応。学校や自治体への提出にそのまま使えます
7-2. 入るなら「梅雨前」の今がベスト!!
保険は、「事故が起きてからでは遅い」もの。特に梅雨の時期は、滑りやすい路面や視界不良による事故が多発します。
お子さんが通学や塾の行き帰りに自転車を使っているご家庭にとって、このタイミングでの加入はまさに“必要な準備”です。
- 前月21日~5日まで申込み分(郵送の場合には5日までに到着した分)→当月15日始期
- 当月6日~20日(郵送の場合には20日までに到着した分)まで申込み分は翌月1日始期
となるため、雨が多い季節になる前に申し込むためには、今がベストです。
8.まとめ│梅雨の自転車は、危険がたくさん
梅雨の時期は、濡れた路面、曇った視界、聞こえにくい雨音など、普段の運転感覚とはまったく違う「見えない危険」があちこちに潜んでいます。
その中を子どもたちは、毎日通学や通塾のために自転車で走っています。これは、親にとっても「守ってあげたい」と感じる大きなリスクのひとつではないでしょうか。
どれだけ気をつけていても、事故は起きてしまうことがあります。だからこそ、日頃の安全対策と同時に、万が一への備え=自転車保険が必要です。自転車保険が義務化されている県も増えてきています。
保険というと、大げさに感じるかもしれません。でも、自転車保険は月140円〜で家庭の経済・心の負担を守ってくれる存在です。
- 通学中に子どもがけがをしても医療費をカバー
- 歩行者にぶつかってしまったときも保険会社が交渉を代行
- 賠償金は最大1億円まで補償
- 加入証明書の発行にも対応で、学校提出もOK
これだけの安心が、スマホから数分で手に入る時代です。
当社では、自転車保険の選び方や補償内容の違いについて詳しくご説明し、お客様の状況に最適な保険プランをご提案いたします。お問い合わせは、当社の公式サイトまたはお電話にて受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。