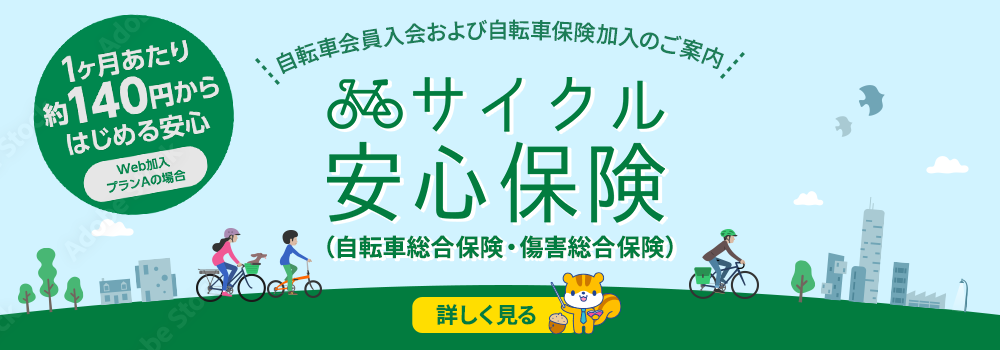「うちの子がそんな大きな事故を起こすはずない」
そう思っていませんか?
でも実は、小学生・中学生が起こす“加害者側”の自転車事故が全国で急増しています。坂道をスピードを出して下っていたら、歩いていたお年寄りにぶつかってしまった——たったそれだけで、9,500万円以上の賠償金を命じられた例もあるのです。
事故の加害者が子どもであっても、その賠償責任は、保護者に降りかかってきます。
最近は全国の自治体で「自転車保険の義務化」が進んでいますが、実は「何に入ればいいの?」「うちはもう火災保険があるから大丈夫じゃないの?」と、正しく理解されていないケースも少なくありません。
今回は、「自転車保険って何?」「うちの子に必要?」「月いくらかかるの?」といった疑問を、初めての方でもわかるように、ゼロからやさしく解説します。
しかも、スマホからたった3分で申し込み可能な保険もご紹介します。
- 自転車保険ってそもそも何?
- 子どもが加害者になったとき、親が背負う“リアルな金銭リスク”
- 義務化されている地域、通学に必要な場合
- 自転車保険を選ぶときのポイントは?
- 家計に優しい、家族型保険のおすすめ3選
- 今すぐスマホで申し込む方法
事故は「まさか」のときに起きます。大切なお子さんを守るために、そして保護者であるあなた自身が後悔しないために、
ぜひ最後までご覧ください。
1.そもそも自転車保険って何?
自転車保険って名前は聞くけど、実際どんな内容か分からない…そんな方のために、基本から分かりやすく解説します。
1-2.自転車保険とは?
自転車保険とは、自転車に乗っているときに起きた事故によって、「自分がケガをした場合」や「他人にケガをさせてしまった場合」などの損害を補償してくれる保険のことです。
たとえば…
- 自転車で転倒して、自分がケガをした
- 通学中に歩行者と接触して、相手にケガをさせた
- 走行中に車にぶつかり、自転車が壊れた
こういった場面で活躍するのが自転車保険です。
1-2.主な補償内容はこの2つ
自転車保険には、主に次の2種類の補償があります。
① 個人賠償責任補償
→「他人にケガをさせた」「物を壊した」ときの損害賠償を肩代わりしてくれる保険
子どもが歩行者に衝突して入院させた、駐車中の車にぶつけてしまった――こんなとき、何百万円〜何千万円の賠償責任が発生することがあります。その金額を代わりに支払ってくれるのがこの補償です。
②傷害保険(本人のケガを補償)
→事故で自分がケガをしたときの医療費や入院費をカバーする保険
- 通院や入院費用
- 骨折や手術にかかった費用
- 後遺症が残った場合の保険金
などを補償してくれます。
1-3.その他の補償(オプション)
保険によっては以下のような補償がついていることもあります。
- 自転車の盗難や破損補償
- 弁護士費用補償
- 救急搬送費用の補填 など
※ただし、今回は「最低限必要な補償」にフォーカスしてご紹介していきます。
1-4.自転車保険はどんな形で加入できる?
保険には「個人型」と「家族型」があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 個人型 | 1人分の補償。本人のみが対象 |
| 家族型 | 家族全員が対象になる。お子さんが複数いても対応可能 |
お子さんが複数いたり、親も日常的に自転車を使う家庭なら、家族型の方がコスパも安心感も上です。
1-5.火災保険やクレジットカード付帯の保険とどう違う?
「すでに火災保険に入ってるから大丈夫じゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、要注意。
たしかに、火災保険やクレジットカードに個人賠償責任補償が含まれている場合もあります。でも以下のような落とし穴があることも…
- 家族全員が対象じゃない(子どもが対象外)
- 通学中の事故はカバー外
- 補償額が1,000万円未満で足りないことも
だからこそ、「本当に必要な場面をカバーできるか?」をチェックすることが大切になります。
2.自転車事故で加害者になるリスク
「うちの子に限って大きな事故なんて…」そう思っていませんか?でも実は、自転車事故による加害者責任は誰にでも起こり得る現実です。では、実際にあった高額賠償の事例と、身近に潜むリスクを見て行きましょう。
2-1. 小学生でも数千万円の賠償命令:実際の事例から学ぶ
実例①:小学5年生の事故で9,500万円の賠償命令
事故概要:2008年9月、神戸市で当時小学5年生(11歳)の男子児童が自転車で坂道を下っていた際、歩行中の62歳女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、意識が戻らない状態となりました。
裁判結果:神戸地方裁判所は2013年7月4日、児童の母親に対し、監督義務違反を理由に約9,500万円の損害賠償を命じました。
この家庭は事故当時、自転車保険に未加入。賠償金は全額、親が負担することになり、経済的にも精神的にも深刻な影響を受けました。
出典:PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
実例②:中学生の事故で5,000万円の賠償命令
事故概要:2005年11月、横浜市で当時16歳の女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で自転車を走行中、前方を歩行中の57歳女性と衝突。女性は重度の後遺障害を負い、歩行困難となりました。
裁判結果:横浜地方裁判所は、女子高校生の過失を認め、約5,000万円の損害賠償を命じました。
このケースでも、加害者である子どもに責任能力はなく、親が“監督責任”を問われて高額賠償を負うことになりました。
出典:長野県公式サイト
2-2. 「いつも通り」の行動が重大事故を引き起こす
事故は、特別な状況で起こるとは限りません。
- 通学中の交差点
- 塾帰りの夕暮れ道
- 友達と並んで自転車を漕いでいた時
- 雨の日のスリップやブレーキの遅れ
どれも日常のワンシーンです。しかし、視野の狭さや判断の遅さが重なることで、重大事故につながるリスクは高くなります。
2-3. 子どもの事故でも、賠償責任は「親」が負う
未成年の子どもが起こした事故でも、法律上では保護者に監督義務があるとされ、賠償責任が親に降りかかるケースがほとんどです。
損害額が数千万円規模ともなれば、家計破綻や人生設計の大幅な見直しすら迫られかねません。
2-4. 月300円の保険で「もしも」の負担がゼロに
もしもの事故が起きたとき、保険に入っていれば
- 被害者への賠償金を保険会社が支払い
- 通院・入院・後遺障害のケア費用もカバー
- 家族の生活・精神的負担も大幅に軽減
これだけの安心が、月にわずか数百円で手に入るのです。
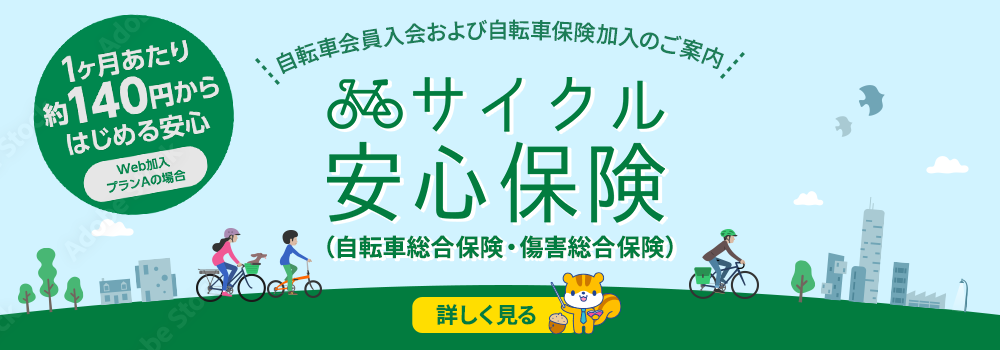
3.義務化が進む“自転車保険”の現状
「保険は任意だから、うちはまだ大丈夫」——そう思っていたら、実はあなたの住む地域では“義務”になっているかもしれません。
3-1. 自転車保険は「義務」の時代へ
かつては、自転車保険といえば「任意加入」が当たり前でした。しかし今では、事故の多発と賠償リスクの高まりを受けて、全国の自治体が次々と条例を制定し、「義務化」へと舵を切っています。
これは一時的な流行ではなく、社会全体の「自転車に乗る人は保険に入るべき」という流れです。
背景は年々増加する「自転車事故による高額賠償」
ここ10年ほどで、自転車事故による損害賠償額が1,000万円以上、時には1億円近くに達するケースが全国で相次いでいます。特に、未成年の子どもによる加害事故では、保護者が「監督責任」を問われて家庭が経済的に破綻寸前になる事例も少なくありません。
こうした事例を受け、自治体は自転車保険を「自己判断で入るもの」から「社会の責任として入るもの」へと位置づけを変えています。
自転車=“軽車両”という事実
道路交通法において、自転車は「軽車両」として分類されています。つまり、自動車やバイクと同様に、他人に損害を与えた場合は“加害者”としての責任が発生するのです。
「子どもが乗るもの」「車ほど危なくない」と軽視されがちですが、実際には、スピード・重量・視認性のすべてにおいて、歩行者にとっては“凶器”にもなり得る存在です。
自治体はなぜ義務化に踏み切ったのか?
自治体が義務化に踏み切った背景には、主に3つの理由があります。
- 加害事故の増加:未成年による人身事故が後を絶たない
- 高額賠償の現実:数千万円の損害賠償が保護者に降りかかるケースが増加
- 被害者救済の必要性:事故後に「加害者が無保険で、賠償が不可能」となる事例の多発
こうした課題に対し、保険加入の義務化は、事故被害者を守り、加害者の家庭を守る両面の効果があると考えられています。
保険加入=子どもを守る“親の責任”
「自転車保険に入っているかどうか」は、今や保護者が担うべき“安全教育と監督責任の一部”ともいえる時代になっています。
自転車事故は、どんなに気をつけていても「完全には防げない」ものです。だからこそ、「事故を起こしてしまった後、家族を守れるかどうか」は保険の有無にかかっていると言っても過言ではありません。
このように、自転車保険は今や「入るかどうかを迷うもの」ではなく、入っておくことが“社会の常識”であり、家庭を守る備えなのです。
3-2. 義務化されている主な都道府県
2024年時点での自転車保険の条例状況一覧は下記の通りです。
| 条例の種類 | 対象都道府県 |
|---|---|
| 義務(34都府県) | 宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 努力義務(10道県) | 北海道、青森県、岩手県、茨城県、富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県、佐賀県 |
| 未制定(3県) | 島根県、長崎県、沖縄県 |
3-3. 義務化されていない地域でも「実質必要」な理由
たとえお住まいの地域で自転車保険が“義務化されていない”としても、実際には「保険未加入だと困る」状況は日常に多く存在します。
以下は、条例とは別に“実質的に必要とされるケース”の代表例です。
(1)通学・通塾時の安全指導で“加入必須”になるケース
多くの小学校・中学校・高校では、「自転車通学許可申請」を行う際に自転車保険への加入が条件となっています。
- 通学用自転車の安全点検チェックリストに「保険加入の有無」の項目がある
- 許可証の交付に「保険証コピー」の提出を求められる学校も多数
また、塾や習い事の教室から「保護者に向けた安全案内」で保険加入を推奨」されるケースも増加中です。
(2)学校行事や部活動でも保険証明が求められることがある
特に以下のような場面では、学校側が「万一の事故に備えて保険加入を確認」するケースが見られます。
- サイクリングイベント、遠足などの校外学習
- 自転車を使う部活動(自転車競技・陸上部のロード練習など)
- 自治体主催の子ども向け交通安全教室
このような場面で、「保険に入っていないから参加できない」となれば、お子さんにとっても残念な思い出になりかねません。
(3)事故が起きた時、無保険だと「社会的責任」を問われるリスク
もしも保険に加入していなかった場合…
- 被害者に対し、加害者(保護者)が全額自己負担で賠償しなければならない
- SNS等で事故が拡散し、「保険に入っていない親」として世間から非難されることも
つまり、義務化されていなくても、「備えていない=無責任」とみなされる風潮が広がっているのです。
3-4. 加入していないとどうなるの?
「義務じゃないから後回しでいい」——そう思っていた矢先に、事故は突然起こります。
加入義務がある地域で未加入だった場合
条例によっては、保険未加入で自転車に乗ることが「違反行為」となる場合もあります。多くの自治体では直接の罰金はありませんが、
- 学校・施設などの利用停止
- 地域の安全指導で指摘を受ける
- 万一の事故時に補償が一切受けられない
など、実質的なデメリットは非常に大きくなります。
加入義務がない地域でも「トラブル」は避けられない
義務化されていない地域であっても、事故が起これば法律上の賠償責任は発生します。その際に保険に入っていなければ、
- 自己資金で数百万~数千万円の賠償を行う必要がある
- 被害者側とのトラブルが長期化し、精神的ストレスや家庭への影響も
また、被害者の中には、「保険に入っていなかった」ことに不信感を持ち、示談が難航するケースもあります。
現代では、未成年の事故に対して、社会や法律の目線が厳しくなっています。「保険にすら入っていなかったのか」と言われないためにも、保険加入は今や親としての責任の一環といえるでしょう。
第4.保険が必要な本当の理由
たとえ小さなミスだったとしても、相手にとっては一生ものの傷になるかもしれない——そんな「取り返しのつかない事態」に備えるための手段が、自転車保険なのです。
4-1. 子どもを「守る」だけでなく、「加害者にしない」ための備え
自転車保険は、「事故を起こしたときの備え」というだけではありません。実はそれ以上に大切なのが、子どもを“加害者にしない”ための準備です。
子どもは好奇心旺盛で、スピードのコントロールや周囲の状況判断がまだ未熟です。注意していても、自転車の運転中にちょっとした気のゆるみで誰かにケガをさせてしまう可能性は十分にあります。
4-2. 保護者には「監督責任」がある
もし子どもが加害事故を起こした場合、責任を問われるのは、保護者です。
法律上、未成年に責任能力がないとみなされる場合、親が代わりに責任を負う「監督義務者責任」が適用されます。
つまり、「保険に入っていなかった」という選択そのものが、事故後に親の監督責任を問われる要因にもなるのです。
- 高額な損害賠償(数百万円〜1億円近く)
- 被害者との示談交渉、通院・後遺症対応
- 近所・学校・SNS上での reputational リスク(評判の悪化)
- 親子ともに「加害者側」として背負う心理的ダメージ
これらすべてが、たった月300円〜500円の保険で回避できるのです。
また、事故後に「保険に入っていなかった」ことが発覚すると、被害者側からの信頼を失い、示談や賠償交渉が難航するケースも少なくありません。相手に誠意を見せる意味でも、事前の保険加入はとても重要なのです。
4-3. ケガをした時の医療費や治療費も安心
自転車保険は、子どもがケガをした場合の補償も含まれていることが多いです。
たとえば…
- 自転車で転倒して骨折
- 段差にタイヤが引っかかって転倒し通院
- 衝突で顔に傷が残り、美容整形手術が必要になった
こうしたときに、治療費や通院費を補償してくれる保険も多数あります。
医療保険ではカバーできないケースでも、自転車保険なら手厚く対応してくれることもあるため、「子どもが乗るものには、子ども専用の保険を用意する」という感覚がとても大切です。
4-4. 「何もなかったら損」は本当か?
「事故がなかったら、保険料はムダになるのでは?」そう思う方もいるかもしれません。
でも、それは違います。
保険は「使うもの」ではなく、“使わずに済んだこと”にこそ価値があるものです。そして何よりも大切なのは、事故が起こってしまったときに、「備えておいてよかった」と思える安心感を持てるかどうか。
損得ではなく、「家族を守るための必要経費」として考えることが、これからの時代の“親のスタンダード”です。
第5章:保険選びで絶対に外せないポイント
「よし、保険に入ろう!」と決めたときに悩むのが、「どれを選べばいいの?」という問題。
自転車保険にはさまざまな種類があり、補償内容や料金もバラバラ。ここでは、子どもがいる家庭が選ぶべき保険のポイントを、絶対に外せない5つの観点からご紹介します。
5-1. 個人型ではなく「家族型」がおすすめ
自転車保険には、大きく分けて「個人型」と「家族型」があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 個人型 | 保険に加入した本人のみが対象(親1人 or 子ども1人など) |
| 家族型 | 同居の家族全員が補償対象になる |
たとえば、親も子どもも日常的に自転車を使う場合、家族型にしておけば1つの契約で家族全員をカバーできます。
料金的にも個人型×2人分より家族型1本の方が割安になることが多く、非常にコスパが良いのが特徴です。
5-2. 賠償責任補償は「1億円以上」が基本
自転車事故で賠償責任が発生すると、損害額は数百万円〜1億円にのぼるケースもあります。そのため、保険を選ぶ際には最低でも1億円以上の賠償補償があるかをチェックしましょう
目安としては…
- 5,000万円以下 → 補償不足の可能性大。注意
- 1億円以上 → 標準的。高額事故にも対応可
- 3億円以上 → 万全レベル。特に都市部では推奨
高額賠償が発生したとき、補償額が足りなければ差額は自己負担になります。「使うことはないかも」と思っても、万一に備えてしっかり上限額を確認しておきましょう。
5-3. ケガや入院の補償があるか?
「自分の子どもがケガをした場合」の補償も、忘れてはいけません。
- 通院・入院・手術費用
- 骨折や捻挫などの軽傷
- 後遺症や障害が残った場合の給付金
こうした補償が含まれていれば、ケガをした際の治療費や通院時の交通費まで補填される場合があります。子どもは転倒や衝突が多いため、「加害者としての保険」だけでなく、「本人の安全を守る補償」も非常に重要です。
5-4. 学校・自治体の要件に合っているか?
通学・通塾・自治体の条例などで、自転車保険に一定の条件が設けられている場合があります。
たとえば…
- 学校側が「賠償責任1億円以上」を必須としている
- 保険証明書の提出を求められる
- 条例で「義務化」されている都道府県に在住
このような場合、条件を満たさない保険に入っていても“未加入扱い”になる可能性があります。必ず、「加入証明書の発行ができる保険」や「証明書のPDFが発行されるもの」を選んでおきましょう。
5-5. 月額コストと補償のバランス
保険料は月額でいうと200円〜500円程度の範囲が一般的です。ただし、料金が安いからといって選ぶと、補償内容が大幅に不足していることも。
理想は、
- 月300円前後で、賠償責任1億円以上
- 家族型で、子どものケガもカバー
- 証明書の発行が可能
こうした保険を基準に選ぶと、費用対効果の高い保険選びができます。
第6章:自転車保険の費用感と内容例
実は、自転車保険は思っている以上に“安くて始めやすい”保険なんです。
6-1. 気になる“お金の話”:自転車保険って月いくら?
「加入した方がいいのは分かったけど、実際いくらかかるの?」多くの方が気になるのが、保険料=コストですよね。
実は、自転車保険は思っている以上に安いものが多いです。
| プランの種類 | 月額保険料の目安 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 個人型(最低限) | 約200~300円 | 賠償責任のみ補償、ケガ補償なし |
| 個人型(充実) | 約400~500円 | 賠償+ケガ補償付き |
| 家族型プラン | 約400~800円 | 家族全員が対象、補償範囲広め |
例えば、月500円の家族型プランに加入した場合、1日あたりたった約16円で「安心」が買える計算になります。
6-2. コストだけで選ぶと失敗する?注意すべき落とし穴
保険選びで「最安値だけ」を基準にしてしまうと、以下のような問題が起こることも。
- 補償額が500万円程度しかなく、高額賠償に対応できない
- 加害者になった場合の示談交渉や弁護士費用がカバーされていない
- ケガの補償が一切含まれていない
- 通学中・塾の行き帰りなど、対象外のシーンが多い
つまり、「月200円なら安心!」と思っても、それで足りる補償かどうかは別問題です。価格と内容のバランスをよく見て選ぶことが大切です。
6-3. 保険は「入って終わり」ではない。更新・証明書にも注意
保険に加入する際は、以下のポイントも事前にチェックしましょう。
- 更新時期の確認:1年ごとの自動更新が一般的
- 保険証明書の有無:学校や通学許可で提出が求められる場合あり
- 補償開始日:加入当日から補償開始のもの/数日後から有効のもの など差がある
特に、学校や自治体からの提出を求められる方は、保険証明の発行があるかを必ず確認しましょう。
7.【スマホで3分で完了】申し込み手順とおすすめ保険
ここまで読み進めてくださったあなたは、「やっぱり自転車保険って必要だな」と感じているはずです。
いまはもう、保険の加入に紙の申込書や面倒な手続きは不要!スマホ1台で、たった3分で加入が完了する時代です。
7-1. 申し込みの基本ステップはこの3つだけ!
多くのネット型自転車保険では、次のような流れで手続きが進みます。
申し込みページにアクセスし、メールアドレスを入力するだけでOK
登録アドレス宛に、保険申込み用のフォームURLが届きます
カード情報を入力すれば、即日で保険加入が有効に
プランによっては「即時発行の保険証明書PDF」もダウンロード可能
7-2. 【おすすめ】損保ジャパンのサイクル安心保険:家族で安心、月額わずか140円〜
はじめての自転車保険なら、月額たった140円から加入できる損保ジャパンの「サイクル安心保険」がおすすめです。
サイクル安心保険の最大の利点は、補償の手厚さと月額料金の安さのバランスが非常に良いこと。
- 賠償責任補償:最大1億円まで対応
- 本人のケガにも対応(通院・入院費用)
- 家族型プランあり(子どももまとめてカバー)
- 加入証明書の発行もOK(通学用にも安心)
- 月額わずか140円台からスタート可能
おすすめポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補償の手厚さ | ◎(賠償+ケガの補償両方カバー) |
| 料金の安さ | ◎(家計にやさしい) |
| 手続きの簡単さ | ◎(メール入力→フォーム記入のみ) |
| 通学・条例対応 | ◎(証明書あり) |
事故は予告なしに起こります。「時間があるときに加入しよう」「今週末にでも」と思っていても、その“今じゃない”わずかな間に、事故が起きてしまったら——もう取り返しがつきません。
だからこそ、自転車保険は「今すぐ」加入するべき保険です。
- 子どもが自転車通学・通塾している
- 家族で自転車を使う頻度が多い
- 保険に入っているかどうか曖昧な方
- 学校や地域から保険証明書の提出を求められている方
- 「安心は欲しいけど、料金は抑えたい」と考える方
8.よくある質問(Q&A)
さいごにサイクル安心保険に関するよくある質問にお答えします。
すでに火災保険やクレジットカードに付帯している保険があるのですが、それで十分ですか?
不十分な可能性もあります。
たしかに火災保険やクレジットカードに「個人賠償責任補償」がついていることもありますが、次のような制限があることが多いです。
▶賠償金額が低い(3,000万円以下など)
▶家族(特に子ども)が補償対象外
▶学校提出用の保険加入証明書が発行できない
そのため、あくまで“補助的な補償”と考え、専用の自転車保険を用意するのが安心です。
申し込み後、いつから補償が始まりますか?
「サイクル安心保険」の場合、月21日~5日まで申込み分(郵送の場合には5日までに到着した分)→当月15日始期
当月6日~20日(郵送の場合には20日までに到着した分)まで申込み分は翌月1日始期となります。
加入証明書はすぐに手に入りますか?
Web上から申込みいただいた場合には、加入者票は郵送されませんのでWeb会員ページからダウンロードをお願いします。
保険は途中でやめることはできますか?
サイクル安心保険から中途脱退される場合、年間掛金のうち損害保険料については、未経過期間の保険料を月割計算にて払い戻しさせていただきますが、制度運営費・年会費の払い戻しはございません。
家族は誰(どの範囲)まで補償されますか?
被保険者の方の配偶者様、同居の親族、別居の未婚のお子様が対象となります
示談交渉サービスはついていますか?
全てのプランに示談交渉サービスが付帯されています。
サイクル安心保険はどんな補償がありますか?
自転車事故補償コース(プランA・B・C共通)
【賠償責任補償】
日本国内において、自転車の所有、使用または管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の賠償責任を負った場合の補償
※業務で自転車を利用中に起こした賠償事故は補償の対象となりません。
(プランB・Cのみ)
【傷害補償】
日本国内において、以下のような事故によってケガを被った場合の補償(仕事で自転車を利用中の事故も傷害保険は補償されます。)
①自転車に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
②他人の運転中の自転車との衝突・接触事故によるケガ
③走行中に他人が運転する自転車との衝突・接触
詳しくは「自転車事故補償コース(自転車総合保険)の補償内容」をご確認ください。
交通傷害ワイド補償コース(プランD・E・F)
【賠償責任補償】
日本国内外において、日常生活に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の賠償責任を負った場合の補償
※業務中の賠償事故は補償の対象となりません。
※自動車・原動機付自転車等の所有、使用または管理に起因する事故は対象となりません。
【傷害補償】
日本国内外において、以下のような事故によってケガを被った場合の補償(仕事で自転車を利用中の事故も傷害保険は補償されます。)
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故
②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災 など
まとめ│保険のご相談はこのまちサポートにお任せ!
お子さんが毎日使う自転車。通学に、遊びに、塾の行き帰りに——自転車は便利で身近な存在です。
でもその反面、事故のリスクは常に隣り合わせ。しかも、小中学生の子どもが事故を起こしてしまった場合、
たとえ加害者が未成年でも、責任はすべて「保護者」にのしかかってきます。
家族を守るためにも、自転車保険に未加入の方は是非ご検討下さい。
当社では、自転車保険の選び方や補償内容の違いについて詳しくご説明し、お客様の状況に最適な保険プランをご提案いたします。お問い合わせは、当社の公式サイトまたはお電話にて受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。